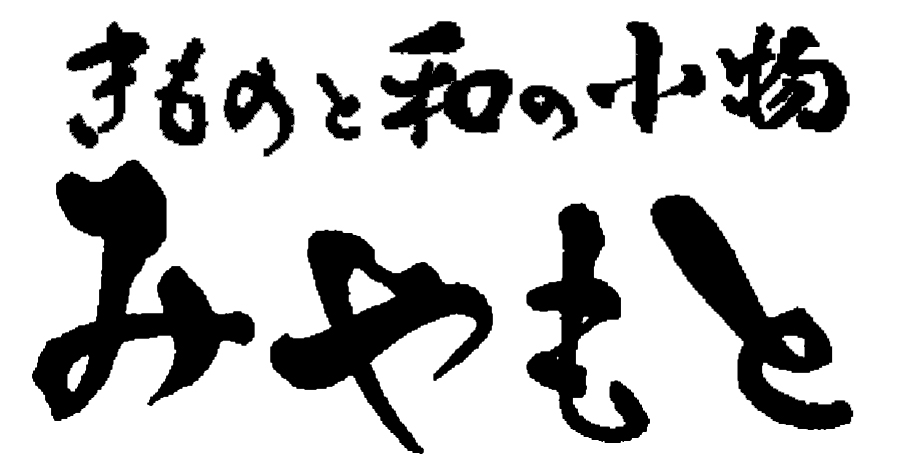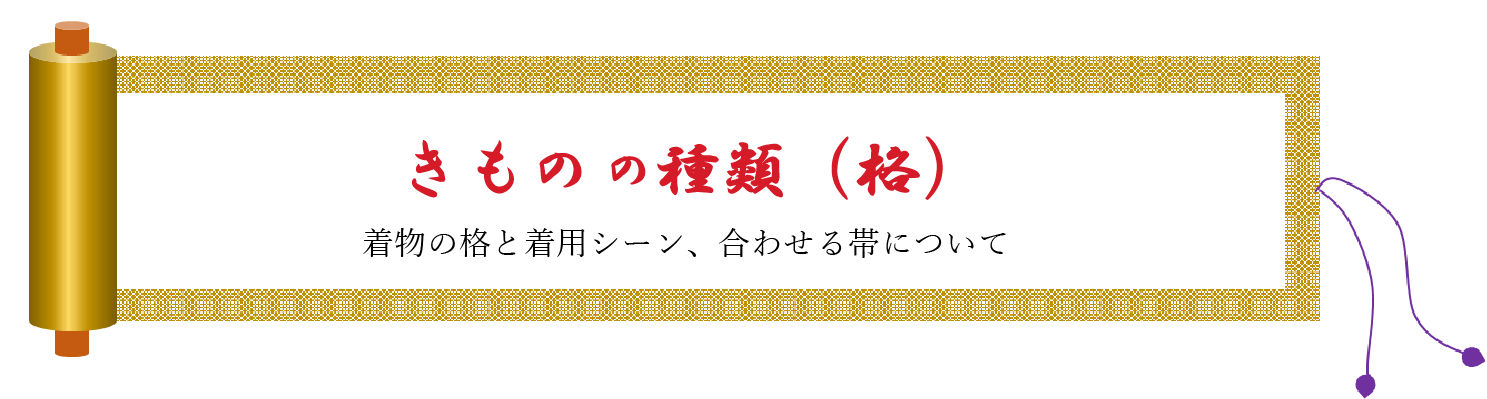
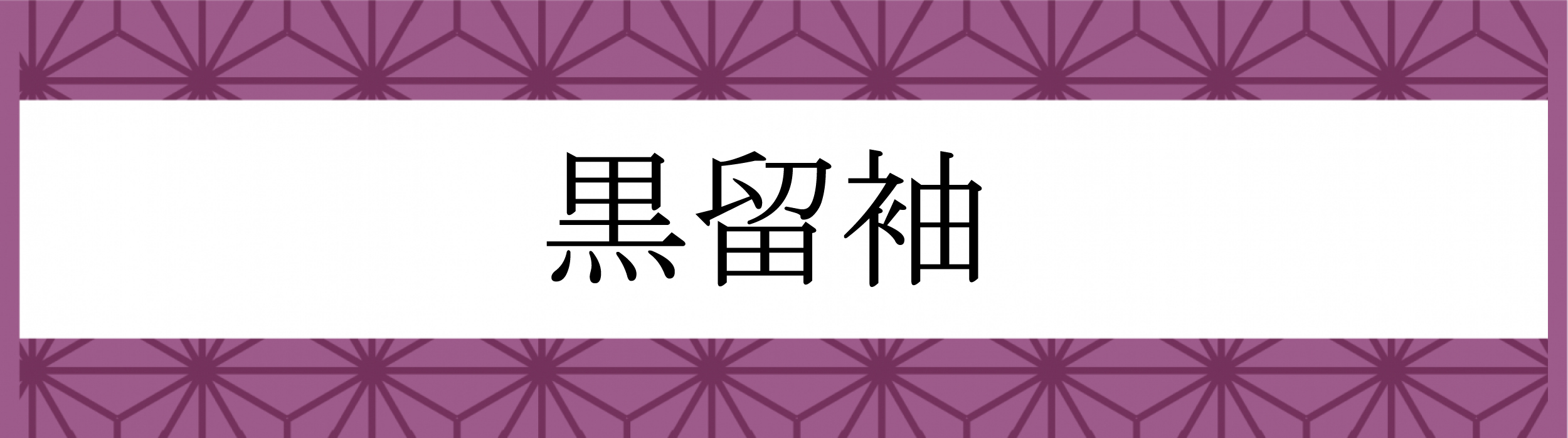

既婚女性の第一礼装であり、最も格の高い着物です。着物の上半身に柄はなく、裾まわりに格調高い吉祥文様を 豪華に染めています。 「染め抜きの五つ日向(ひなた)紋」「白の比翼仕立て」という2点が 決まり事です。制作時点で想定年齢があって作られており、 色柄によって若向き、年配向きと分かれます。 第一礼装である黒留袖の着用時は、帯や帯締めなどの小物も、 留袖に相応しいものを選びましょう。
【利用できるシーン】
・新郎の母親や祖母として参加
・関西などでは親族として結婚式に参加する場合も着用
【おすすめの帯】
金、銀、白などをベースとして、豪華な吉祥文様が織り上げられた 「袋帯」がベスト。
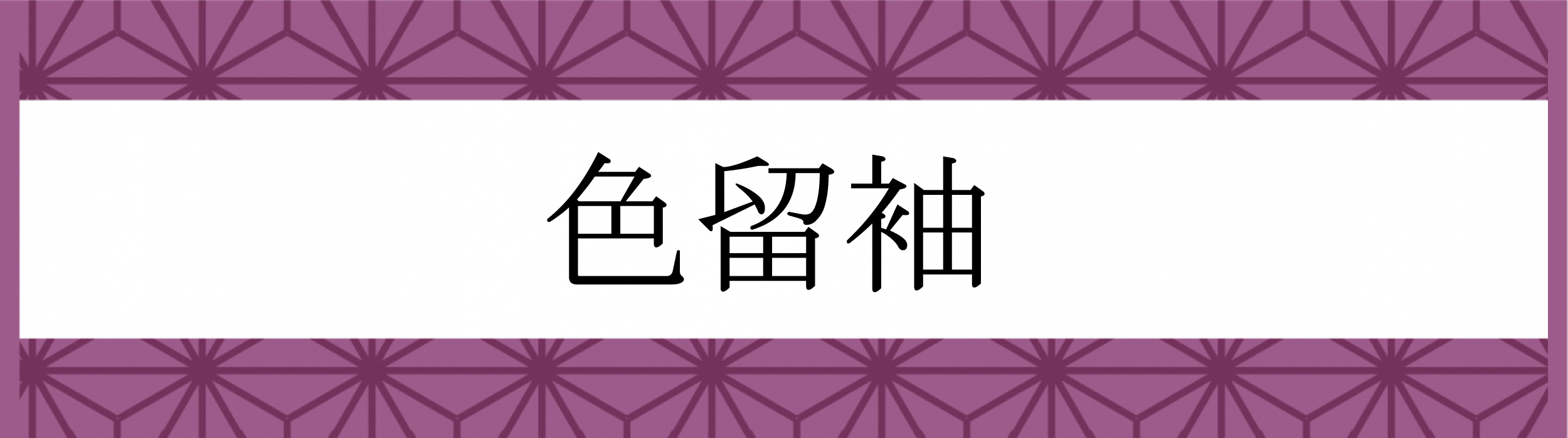

【特徴】
色留袖は、黒留袖と同じような裾模様で、地色は黒以外の色で染められた着物。五つ紋が付いていれば黒留袖と同格。主に既婚女性が礼装として着用します。一般的に紋は三つ紋か五つ紋が多いですが、控えめな柄の場合は一つ紋にすることも可能です。黒留袖は着用シーンが限られますが、三つ紋以下の色留袖は招待された結婚式などにも着用でき、黒留袖よりは幅広いシーンで着用できます。関東では新郎新婦の親族もよく着用します。皇室において黒は喪の色とされているので、叙勲は色留袖となります。
【利用できるシーン】
・結婚式
・勲章(叙勲)、文化勲章、褒賞の伝達式
・祝賀会
【おすすめの帯】
金、銀、白地で織られた豪華な「袋帯」を基本とし、地色は金銀白以外であっても構いません。色留袖の地色、柄と調和したものを選びます。
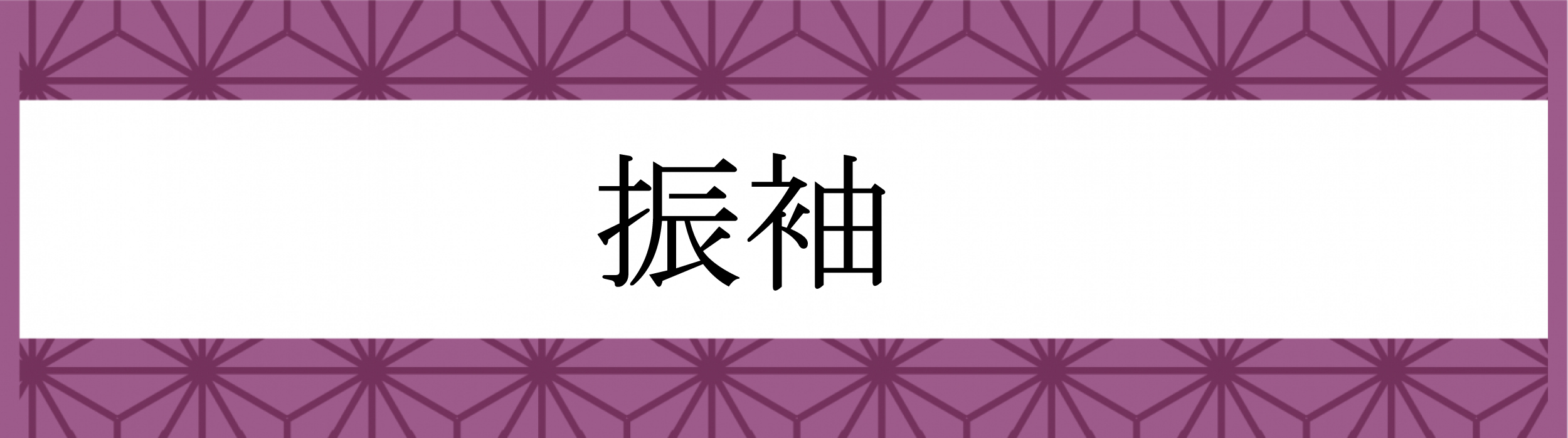

【特徴】
未婚女性の第一礼装とされ、袖の長さによって「本振袖」「中振袖」「小振袖」に分類されます。以前は中振袖がメインでしたが生産側の理由で、現在は本振袖が主流。本来は紋が付いてしかるべきですが、慣習的に紋は付けていません。「袖を切ったら訪問着になる」との意見もありますが、振袖は華やかで若々しい柄が描かれているので、訪問着としての利用は難しいことが多いのです。最近は若いミセス(既婚者)も振袖を着用する場合があります。
【利用できるシーン】
・成人式
・未婚女性であれば、招待された結婚式・披露宴
・自身の結婚式
【おすすめの帯】
振袖用に織られた格の高い「丸帯」「袋帯」を締めます。成人式やパーティなど、晴れの舞台では結び方をアレンジして若々しさを演出するのが素敵です。
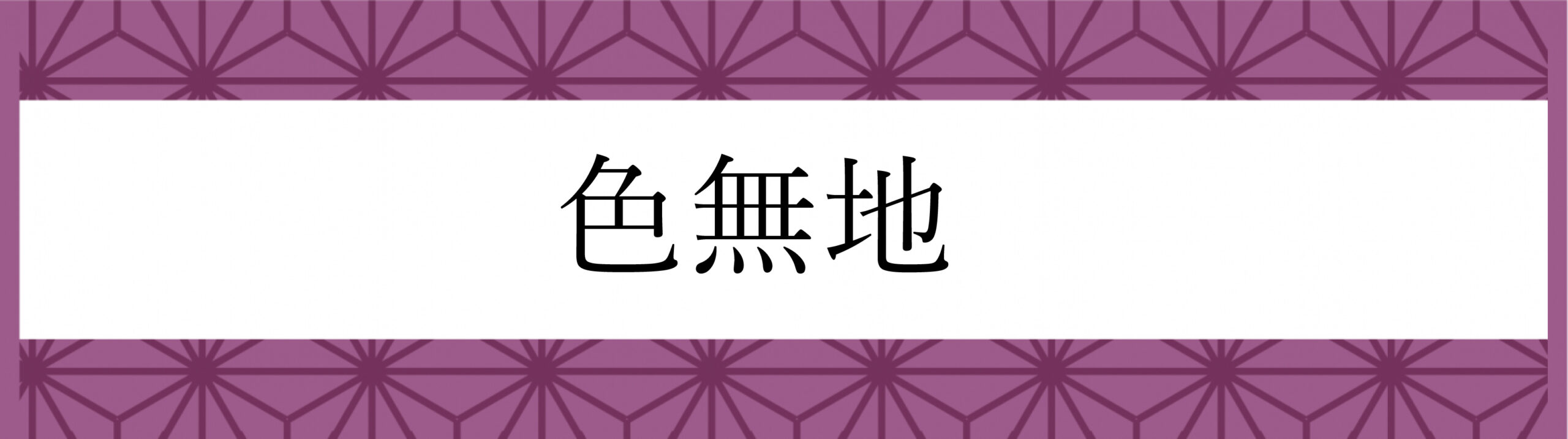
【特徴】
色無地は、白生地を黒以外の1色で染めた着物です。色無地には、綸子(りんず)などの地紋が織り込まれたものと縮緬(ちりめん)などの地紋のないものの2種類があります。フォーマルな場面で着ることができるのは、地紋がある色無地です。地紋がない色無地は、カジュアルシーンに着用できます。
【利用できるシーン】
・五つ紋や三つ紋の付いた色無地は、格の高い略礼装のフォーマルな着物になります。結婚式や入学式、卒業式などの式事や正 式なお茶会など。
・一つ紋付の色無地の場合は、訪問着や附下げと同じ略礼装の着物になります。結婚式やパーティー、お茶会など着用範囲が広いため、色無地を仕立てる際は一つ紋付にされる方が多いようです。
・紋を入れない色無地の場合は、小紋や紬と同じ普段着の着物になります。カジュアルなお洒落感覚で普段着としても着用できます。
【おすすめの帯】
・五つ紋や三つ紋の付いた色無地は、礼装用の袋帯。
・一つ紋付の色無地の場合は、品格のある袋帯や、綴れ織の名古屋帯など。
・紋を入れない色無地の場合は、名古屋帯や半幅帯など。


【特徴】
訪問着とは、上半身から裾までを1枚のキャンパスに見立てて、豪華な柄が染められた着物のことです。留袖同様に「絵羽(えば)付け模様」と呼ばれ、縫い目で柄が繋がるように染められます。訪問着と一口に言っても、柄の格調高さや量によって着用シーンは様々です。控えめな訪問着に一つ紋を付けて準礼装とすることもあれば、豪華な柄の訪問着でも紋を付けず盛装とすることもあります。
【利用できるシーン】
・結婚式など冠婚祭
・パーティー
・茶道のお茶事
【おすすめの帯】
留袖に合わせるような豪華な「袋帯」から、金銀糸を使っていない唐織の「袋帯」まで。訪問着の雰囲気に合わせた格の袋帯を締めることが大切。

【特徴】
付け下げとは、フォーマル着物のなかでも控えめな柄付けの着物を指します。訪問着の絵羽付けを簡略化してあり、準礼装であっても控えめに装いたいシーンに相応しい着物です。帯や小物との組み合わせ次第で格を自由に変化させられるので、最も幅広く活用できます。
【利用できるシーン】
・茶道のお茶事
・入学式や卒業式への付き添い
・七五三などの付き添い
【おすすめの帯】
「袋帯」から「名古屋帯」まで合わせられます。ただし付け下げ着物の雰囲気、
格調に合わせることが必須です。帯や小物によって格調高くも仕上がりますし、
控えめな付け下げであれば染めの名古屋帯でも構いません。
綴れの八寸名古屋帯(袋名古屋帯)なども。